日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録
2024年12月5日にこうじ菌を使った日本の「伝統的酒造り」の技術がユネスコ無形文化遺産に登録されました。どんな内容で、どのような影響があるのでしょうか? 日本酒や本格焼酎のメーカーでつくる日本酒造組合中央会の記者会見を取材しました。

日本酒だけでなく本格焼酎・泡盛、本みりんも!
会見では最初に同会の副会長で「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会」の会長を務める小西新右衛門氏が喜びを語りました。
「日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりんという日本の伝統的な酒造りのすべてが登録の対象となった。これはこうじ菌を使った酒造りという括りで、国内では3年前に登録無形文化財に登録されたが、ユネスコでの登録にはさらに3年を要した。ご尽力いただいた皆さまに心から感謝を申し上げたい。日本では穀物の粒のままこうじ菌を繁殖させるバラ麹を用いる。日本で独自に発展したもので発酵文化の基となっている。登録は、そうした酒造りの技術の伝承であり、麹への理解を促す活動をしっかりやっていく」

さらに日本酒造杜氏組合連合会の石川達也会長の言葉を代読し「(前略)酒造りの伝統技術は無形の文化遺産ですから、言語化・数値化した記録として保存すればいいというわけにはまいりません。その技術を継承していくのは、あくまで『人』なのです。したがって、酒造りの世界に意欲のある人が入り、伝統技術を体得していくことの可能な環境を整えることが必要になります(後略)」と続けました。

ソムリエが料理と日本酒のペアリングに注目
また、登録の喜びを聞かれた宇都宮仁氏は「うれしいと同時に『しっかり伝えていけ』と書かれており、検証もしていかなければならないのでプレッシャーも感じている。これまでも子供向けの麹造り体験会などいろいろ進めてきているが、さらに麹を使った酒造り技術を知る機会を設けていく」と述べました。


ユネスコ無形文化遺産登録が国内外での國酒の評価を高める
ここで今回の登録の意義を考えてみましょう。2013年に和食が無形文化遺産に登録された時にユネスコ大使であった門司健次郎氏は自身のSNS(Facebook)で次の3つを挙げています。
第1は、登録により、日本の伝統的な酒類は、単なるアルコール飲料ではなく、日本の文化である、と広く内外に宣言されることです。
第2は、登録は、日本酒の存在を多くの日本人に再認識させるであろうということです。今日、日本酒は日本の社会生活の中で存在感を失ってしまいました。登録が話題になることにより、人々が全47都道府県にある地元の酒蔵に目を向けるようになることを期待します。
第3は、登録は、伸びつつある海外市場で日本酒の強い後押しとなることです。和食の登録が更なる和食ブームにつながったことが想起されます。
門司氏が指摘するとおり登録が契機となり和酒に関心が向けられ、国内で再評価の機運の高まりが期待できる。海外でも単なるアルコール飲料ではなく豊かな文化をもっているという理解を促すでしょう。
「どぶろく」にもスポット
けれど自家醸造が禁止されてからどぶろくは公の場から排除され、伝統的な酒でありながら酒造りの技術の継承と発達機会を失いました。近年のクラフトサケ(フルーツやハーブなどの副原料を使った新しい米の醸造酒造り)の取り組みは、どぶろくの失われた一世紀を回復する運動と見ることもできます。

「麹」は日本の発酵食品の大元
酒や味噌・醤油の製造業が成長するとともに、特殊な技術と設備が必要な種麹造りは外部の専門業者に任されるようになり、有力な業者に集約されて今日に至っています。多くがBtoB取引で一般的に知られていない種麹屋に関心が寄せられ、日本の発酵食品文化を支える存在であると知られることは有意義なことです。


※記事の情報は2024年12月19日時点のものです。
『さけ通信』は「元気に飲む! 愉快に遊ぶ酒マガジン」です。お酒が大好きなあなたに、酒のレパートリーを広げる遊び方、ホームパーティを盛りあげるひと工夫、出かけたくなる酒スポット、体にやさしいお酒との付き合い方などをお伝えしていきます。発行するのは酒文化研究所(1991年創業)。ハッピーなお酒のあり方を発信し続ける、独立の民間の酒専門の研究所です。
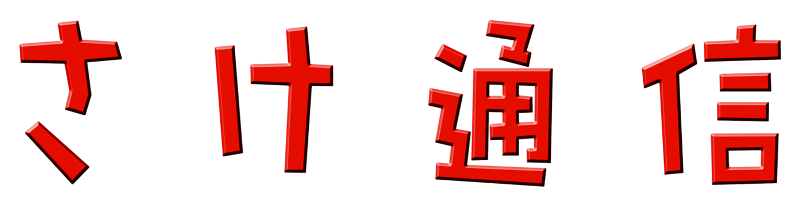
- 1現在のページ
 山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)
山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)