木桶仕込みの再評価を考える。ホーローから木桶に戻す理由とは?
近年、発酵食品の製造現場に木製の道具を再評価する動きがあり、発酵工程を木桶でおこなう清酒や味噌・醤油の蔵が増えています。なぜ、いま木の道具なのか、一度、ホーロータンクに変わった発酵槽を木桶に戻す理由を探ってみましょう。

酒の「木桶仕込み」は復活から20年
そこに伝統的な木桶での酒造りを復活させるプロジェクトが立ち上がります。主旨に賛同した酒蔵は、地元の杉の木を伐採して大桶を作ったり、吉野杉の大桶を特注したりして「桶仕込みの酒」を発売し、話題になりました。その後、2005年に発足したNPO法人桶仕込み保存会には約30の酒蔵が参加し、多い時には50蔵を超えました。

立ち上がったのはずっと木桶で醤油を造ってきた山本康夫さん(ヤマロク醤油株式会社)です。小豆島から桶職人の上芝雄史さん(藤井製桶所・大阪府堺市)の下に足しげく通い、大桶作りの技術を習得します。桶屋がなくなれば、新桶の供給も修理もままなりません。自ら桶職人となることで危機を乗り越えようとしたのでした。
さらに彼は木桶職人復活プロジェクトを立ち上げ、大桶作りを継承する有志を募り、ネットワークを広げます。今では、毎年1月に小豆島で開催するワークショップ「木桶による発酵文化サミット」は、全国から味噌や醤油や酒のメーカー、木桶仕込みの発酵食品に関心を持つ料飲店や流通関係者などが大勢集まる一大イベントとなっています。
こうした動きの中で人気酒造(福島県二本松市)は市販酒をすべて木桶で仕込み始め、新政酒造(秋田県秋田市)も全量秋田杉の木桶での仕込みを目指すなど、本格的に木桶仕込みに転換する酒蔵も出てきました。



木の大桶は衛生管理と冷却に難
清酒造りの技術は江戸期には確立し、旺盛な需要に応えるために大規模化が進みます。精米は手搗きから足踏み搗き、さらに水車精米になり、蒸米工程では10石(1500kg)の米を一度に蒸せる大釜が導入され、これは大量の酒の火入れ(加熱殺菌)も可能にしました。仕込み桶も大きくなり一度に10石を仕込める大桶が登場すると、醪(もろみ)の発酵熱を発散させる冷却が必要になり、寒造りが主流になりました。
灘の酒蔵の建屋はどこも東西に長くなっていますが、北から吹きつける六甲おろしを正面で受け、蔵の温度を下げるためと言われます。

早い蔵は大正期から昭和初期に導入が本格化したようですが、灘では昭和なってもしばらくは木桶が使われました。技術革新は辺境から始まると言われますが、酒質の向上を課題と認識していた意欲的な地方蔵が積極的に導入し、酒の評価が高かった主産地はあえて酒造りを変える理由がなく、すぐにはホーロータンクへの転換が進まなかったのかもしれません。
また、大浦和也さん(白鹿記念酒造博物館学芸員)は戦時下の金属供出が転換を進めたと指摘します。灘ではホーロータンクの前に銅製のタンクが導入され、これを供出する代わりに提供されたのがホーロータンクでした。なお、こうした経緯から銅製の仕込みタンクは残っていません。
こうして1960年頃までには酒蔵で木の大桶が使われなくなり、ホーロータンクが主流になります。さらにステンレスタンクが登場し、近年は冷却できるサーマルタンクが導入されてきました。


木桶仕込みに複雑味を期待
2006年に桶仕込み保存会のセミナーを聴講し、即座に木桶の導入を決めた酒井酒造(山口県岩国市・「五橋」製造元)の例を見てみましょう。2009年のインタビューで酒井佑社長(当時)はその理由を、長くおいしい酒を安定的に合理的に造ろうと努めてきたが、少し前からこのまま進んで行っても魅力的なものにならないのではないかと予感していたと述べました。そして、木桶仕込みで複雑味のあるおいしさを目指そうと考えた、と続けました。
前出のヤマロク醤油の山本康夫さんは、木桶で仕込んだ醤油はまろやかで味に幅が出ると言い、フレッシュでクリーンな量産型の醤油と一線を画した高付加価値商品として木桶仕込み醤油のブランド化を図っています。次々に木桶仕込みを始めた醤油蔵たちは、官能評価で同様に感じ、この考えに賛同し共に取り組んでいます。ただし、一般的な醤油との成分の明確な違いや、おいしくなるメカニズムの科学的な裏付けは検証途上です。
裏付けを持って木桶での仕込みを再導入したのはサントリーでした。1989年の山崎蒸溜所の大改修でサントリーは、多彩なウイスキー原酒を得るために木製発酵槽を再導入しました。一度はステンレス製の発酵槽に切り替えたのでしたが、複雑な菌叢(きんそう)となる木製発酵槽からは重厚な味わいの原酒を得られるからです。また、ウイスキー製造開始から100年となる2023年、同社はフロアモルティング(大麦を床に広げて発芽させ麦芽を作る伝統的な製法)を山崎と白州の両蒸溜所で復活させます。フロアモルティングで作られた麦芽の他の麦芽との違いや香味への影響を研究するとしています。
現代の技術やインフラを用いて伝統製法に取り組み、その特徴を明らかにする試みは、新しい発見につながる。そうした意識は酒の種類によらず、造り手にも飲み手にもあるようです。良質な酒を量産できる今、感動のある酒は未知の分野の探索から生まれると直感しているのではないでしょうか。

※記事の情報は2025年2月6日時点のものです。
『さけ通信』は「元気に飲む! 愉快に遊ぶ酒マガジン」です。お酒が大好きなあなたに、酒のレパートリーを広げる遊び方、ホームパーティを盛りあげるひと工夫、出かけたくなる酒スポット、体にやさしいお酒との付き合い方などをお伝えしていきます。発行するのは酒文化研究所(1991年創業)。ハッピーなお酒のあり方を発信し続ける、独立の民間の酒専門の研究所です。
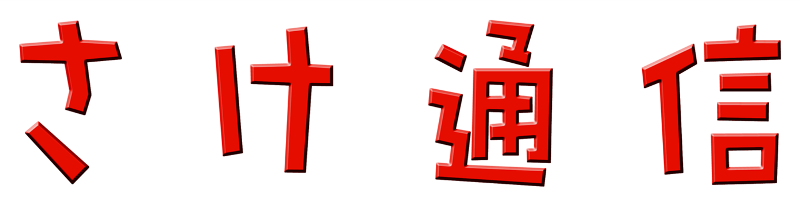
- 1現在のページ
 山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)
山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)