樽作りの技術を継承する、菊正宗酒造「樽酒マイスターファクトリー」
今でも日本酒に欠かせない木の道具のひとつは樽です。祝い事で鏡開き(樽の鏡板を木づちで叩いて割るセレモニー)や樽酒づくりに杉の樽が欠かせません。長年、樽酒をリードしてきた菊正宗酒造の「樽酒マイスターファクトリー」を訪ねました。

瓶入り樽酒のパイオニア「菊正宗」
樽作りをまるっと解説、「樽酒マイスターファクトリー」
樽酒の製造には大量の樽が必要です。菊正宗酒造は毎年数千樽を調達していますが、取引先の製樽所の廃業に伴い、必要な樽の一部の内製化に踏み切りました。製樽所から機材を譲り受け、職人を引き継いで技術継承を図っています。そして、樽作りの様子を公開し、その魅力を伝える施設を作ったのでした。

見学できるように設計されていますが、主目的は樽の製造です。毎日、職人たちは竹を割って箍(たが/樽を締める竹の輪)を編み、側板(がわいた/樽の側面の板)を寄せ、箍を締め鉋(かんな)を掛けて、ひとつひとつ手作業で仕上げていきます。接着剤や釘を使うことなく酒が漏れない樽を作る様子に、多くの人が感銘を受けることでしょう。
おいしい樽酒に欠かせない吉野杉
樽酒は酒税法の規定で清酒を一度樽に詰めなければなりません(杉材のチップを浸漬したものはリキュール規格で清酒と表示できない)。天然材の樽を使うため樽酒の香味は樽ごとに異なります。けれども、たくさんの樽酒を合わせると香味は一定の範囲に収まっていきます。官能検査を経て、「菊正宗樽酒」としてふさわしいものだけが製品となります。

生酛造りは木の半切り桶と暖気樽で
同社は12月から2月中旬まで、昔ながらの木製の半切り桶と呼ばれる直径1m強、深さ50cmくらいの容器で酛を造ります。木製にこだわるのは桶に棲みついている乳酸菌を活かすためです。ステンレス製の桶では殺菌されて菌は残りませんが、木製の桶には残ります。実際に約20年前に分離した菌と同じ菌が、今の桶からも採取されています。この菌が「菊正宗」の味につながっているのでしょう。
生酛造りは半切り桶で、蒸米、米麹、水を混ぜ、擂り潰します。そして半切り桶八つ分をひとつの酛桶に集め、酵母が増殖しやすい環境を与えます。持ち手のある暖気樽という木樽に熱湯を詰め、これを酛桶に入れて昼間は温め夜は冷ましを繰り返し、乳酸菌を増殖させて酸性に誘導します。すると次第にアルコール発酵する酵母が旺盛となり、生成されたアルコールで乳酸菌が死滅して酵母の塊、本発酵のスターターである酒母ができあがります。温めたり冷ましたり、分けたり集めたりする手間と時間のかかる伝統技術です。
なお、暖気樽は樽と呼ばれていますが、何年も繰り返し使用されるという点では桶の仲間と言えましょう。半切り桶と同じく箍を毎年交換しますが、これは樽とは締め方が異なる桶職人の仕事、菊正宗酒造では桶職人を抱える剣菱酒造の木工所に委託しています。



菊正宗樽酒マイスターファクトリー公式サイト
菊正宗酒造記念館公式サイト
※記事の情報は2025年2月20日時点のものです。
『さけ通信』は「元気に飲む! 愉快に遊ぶ酒マガジン」です。お酒が大好きなあなたに、酒のレパートリーを広げる遊び方、ホームパーティを盛りあげるひと工夫、出かけたくなる酒スポット、体にやさしいお酒との付き合い方などをお伝えしていきます。発行するのは酒文化研究所(1991年創業)。ハッピーなお酒のあり方を発信し続ける、独立の民間の酒専門の研究所です。
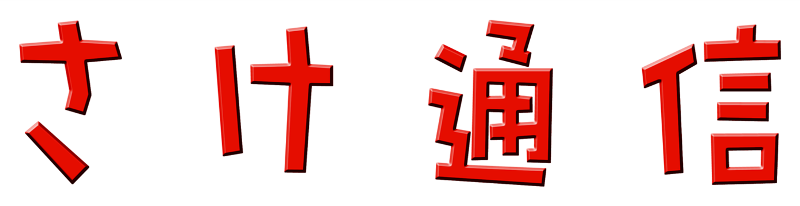
- 1現在のページ
 山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)
山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)