どぶろく最前線⑧ “どぶろく”を知ると酒の歴史が腑に落ちる
シアトル出身のジャスティン・ポッツさんは日本の酒蔵で働き、今はアメリカでSAKEブルワリーの経営に携わっています。日本の発酵食文化に精通すると同時に異文化の視点を持つ彼が、“どぶろく”をどのように見ているか聞いてみました。

日本の食事で身体が元気になった
ジャスティン どうして関心を向けるようになったのか振り返ってみると、大きなきっかけは二つだったように思います。
ひとつは私自身の体調の変化です。幼い頃、身体が弱くて、20歳になる前くらいまでは年に1回くらい入院するほどでした。ですが大学生の時に食べるものを変えることで体調がよくなる経験をします。肉を食べないとか、トレーニングするとか、ストイックな生活にすると体調は良いのです。ですがそれを続けるのはとてもたいへんで、現実的ではないと感じていました。
私は旅行が好きで、その頃欧州や南米、アジアなどを周ったのですが、タイと日本に行った時に体調がよくなったのです。特別なものを食べたわけではなく、普通に現地の人が食べているものを食べただけで。日常食を変えるだけで、身体は変わるのだと身をもって知ったのです。
―日本で暮らすようになったのは?
ジャスティン 次に日本に来たのは留学です。必要な単位を取り終えてから、卒業するまでにどこかに留学したいと教授に相談すると、イタリアと日本ならチャンスがあるというので、じゃあ、日本にしますと。日本語は高校で授業をとりましたが、ほかの人がやっていないものをやってみようと思っただけで、ひらがなが半分読めるかどうかというレベルでした。
4か月間、大阪で過ごしましたが、もう日本に来ることはないだろうから、ここでしかできないことをどんどんやろうと思ったのです。アメリカで食べていたものは食べないと決めて、お金はないのでほとんど毎日、安い居酒屋で食べていました。
―日本酒に馴染んだのはその時ですか?
ジャスティン そうですね。シアトルはクラフトビールが盛んで、良質なワイン産地でもあるので、学生でもそこそこおいしいビールやワインに触れています。ところが当時の日本の居酒屋で出て来るワインは相当怪しいものばかリで、ビールはおいしいけれど、どの店に行っても同じスタイルでした。
それで日本酒を試してみました。感動したわけでも、おいしいと思ったわけでもなかったのですが、居酒屋でみんなと飲む場に自分がフィットした気がして、お酒を飲むところに行ったら日本酒にすることにしました。普通の安いお酒でしたが、しばらくするとこれでいいんじゃないかなという気持ちになりました。

“麹”との出会いで発酵食品に開眼
ジャスティン その後、仕事やプライベートでアメリカと日本を何度か行ったり来たりするようになって、ある時、自分は日本の食べ物をまったく知らないと知る体験をします。それが発酵食品に興味を持つようになったふたつ目のきっかけです。
妻と付き合うようになって彼女の家に遊びに行くと、出してくれる料理は見たこともないものばかりでした。どれもシンプルなのだけど居酒屋で食べてきたものよりよほど美味しくて、今まで自分は日本の食べ物をまったく知らなかったと思いました。義母は岩手、義父が宮崎出身だったので、彼女の両親の郷土料理を作って出してくれたのですが、そうしたものを誰も紹介しようとしていないのだということにもまた気づきました。
日本の食に対する関心の高まりに拍車をかけたのは、六本木農園で仕事をするようになったことです。ファームトゥテーブル(農場から食卓へ)というコンセプトで、各地の熱心な作り手の農産物をエンターテイメントの要素を入れながら紹介するレストランでした。毎日ウエイターとして店に立ち、食材や料理について勉強し、食べて味を覚えて説明すると、お客さんは「なにそれ?」という感じで、実は使用されている食材について何も知らないで料理をオーダーしていました。
地域プロデュースもやる会社だったので、週末ごとに生産者を訪ね歩きました。意識の高い農家や醸造家の方たちの話を聴き、製造の現場を見て、そのうちに“麹”を知ります。種麹屋さんとの出会いは衝撃で、日本の発酵食品のすべてを束ねているのだと気づいて、パッカーンと蓋が開いたような気分でした。海外には味噌を知っている人はたくさんいますが、麹について彼らは何も知りません。
麹はすごすぎる!と思いましたが、塩麹や甘酒が話題になる前だったので、ネットで検索してもなかなか出てきませんでした。当時、麹はネットにすら答えがなかった、当たり前なのにまったく知られていませんでした。ぬか床で漬けた野菜からは味覚を超える、身体が喜ぶようなおいしさを感じます。ここに何かあるのではないか、一生かけて麹を追いかけて損はない、得することしかないぞと思ってからは、日本の発酵食品にのめり込みました。

現代の日本酒から遡る違和感
ジャスティン 初めて飲んだのは真冬に新潟の豪雪地帯、山のなかの祭りだったと思います。その後も接点がなかったわけではありませんが、逆にあまり出会わないことに違和感がありました。
違和感は日本酒を知るにつれて鮮明になって行ったように思います。麹を学ぶのに手っ取り早いのは酒なので、酒蔵を見学したり、作業を手伝わせてもらったり、蔵の方々と一緒に飲んだりして、知識と経験を深めていきました。日本酒の資格もあったほうがいいかもしれないと思って勉強してみると、レクチャーに出て来る酒と、蔵人と一緒に体験した酒にギャップを感じました。
―どんなギャップですか?
ジャスティン 日本酒のレクチャーでは最初に歴史・文化から始まることが多いですけれど、古代から始まって1時間くらいするといきなり現代、1990年以降に飛んで、そこからは最近の価値観で日本酒を説明していきます。でも、それはちょっと違うのではないかと思う。酒蔵に行けば精米歩合とか吸水率とか説明してくれますが、一緒に飲んでみるとごく普通の酒を楽しく気持ちよさそうに飲んでいます。杜氏さんがふだんの生活の中に置いているのは普通酒だったりして、そっちのほうがよほどいいのではないかと。
今は大吟醸や純米酒に目が向けられていることはわかります。ですが、日本酒に馴染んでいる人の普段の生活に溶け込んでいるのは普通酒です。それを見ないのは「ちょっとおかしいのでは?」というギャップです。どぶろくも同じで存在を無視して、最近の価値観で見た酒の話をしている気がします。
どぶろくは日本酒の原点だと言いますが、リスペクトされていません。にごり酒も、たとえば酒蔵たちが自分のところの酒を3本ずつ持ち寄って飲もうとなった時に、にごり酒を持ってくる人はほとんどいないでしょう。にごり酒はおいしいし、海外では日本酒を見る基準がわからないから、にごり酒はおもしろい、“映える”と言われます。海外から求められているのに、皆、持って行こうとしないのはなぜなのでしょう。

どぶろくの直感的わかりやすさ
ジャスティン 酒類全体を見渡せば消費の多様化が進んでいます。おいしいのは当たり前で、それだけで残っていける時代は終わっています。しっかりしたアイデンティティがないと流行り廃りですぐに消えてしまいますから、そこでしか味わえない世界が大切で、そういった意味でもどぶろくが重要になってきます。
―「どぶらぶ(どぶろくを愛でる会の略称)」でどぶろくアンバサダーを引き受けたのは、どんな経緯でしたか?
ジャスティン 代表の大越さんがSNSで「どぶろくに向き合って、『どぶらぶ』をやります」と発信したのを見て、まさにこれだ!と思い、私からやらせて欲しいとメッセージを送りました。すぐに「日本酒の教育の中でもっとも重要な部分だからすぐに来て」と返事があり、直接会っていろいろ話し合いました。
―自家醸造が認められている海外では、どぶろくづくりを趣味にする方も増えていると聞きます。
ジャスティン そうですね。ただ、まだ、海外のSAKEファンのほとんどは、どぶろくを知りません。彼らに日本酒の原点だと説明すると「教えて欲しい」となって、どぶろくを見せるととてもわかりやすいと言います。日本酒は説明しないとわからないけれど、どぶろくはすぐにわかる。見ただけで米の酒だとわかるし、美味しいものもある。
麹を学ぶツアーで日本に来た外国人シェフたちに某どぶろくを飲ませたら、「これがどぶろくですか!すばらしい」と絶賛されました。どこで手に入るのかと聞かれましたが、なかなか買えない(笑)。
―生のどぶろくは流通が難しいですし、製造量も限られていて、あまり店に並んでいません。

「どぶろくとは?」を改めて考える
ジャスティン 実は定義がないので難しいところがあります。どぶろくは酒税法では清酒に対して「濾さないもの」と線が引かれていますが、どぶろくそのものについては何も決まったものがありません。
最近、その他の醸造酒の免許で、若い人たちがいろいろな米の醸造酒づくりにチャレンジしていますが、古老が伝えるどぶろくのレシピ集『諸国ドブロク宝典』(農文協刊)を見れば、雑穀を使ったり副原料を加えたりするものは昔からありました。反対に当然ですけれど清酒で発展した生酛(きもと)の三段仕込みのどぶろくはなかった。これらの技術が確立する前はどんな酒だったのかという視角で酒を見ている酒蔵もあって、島根の酒蔵がその他の醸造酒の製造免許をとって、雑穀のどぶろくをつくりました。あれはとてもいい試みだと思います。
―どぶろくとは何かをあらためて考える必要がありますね。
今、少し専門的なワードが出ましたので清酒にあまり詳しくない方のために補足しますと、酒を造る免許はビールとか清酒とか酒の酒類別になっています。米を発酵させて造るどぶろくは「その他の醸造酒」の免許になります。その免許だと清酒にミカンやリンゴなどのフルーツやホップやミントを加えることもできるので、あえて「その他醸造酒」の免許で酒を造るメーカーが出てきています。
また、生酛というのは江戸期に確立した清酒の製法で、今もこの造りにこだわっている酒蔵があります。もうひとつのワード、三段仕込みは、原料の米を三回に分けて仕込んでいく手法です。一度にたくさんの米を発酵させようとすると、発酵が追い付かず雑菌に汚染されて失敗するリスクが高いのです。それで最初に少量造って、発酵が進んで安定したら二回目の米を加える、さらに三回目と増やしていきます。これも江戸期に酒造業が産業化していく過程で生まれた製法です。
ジャスティン 山田さん、わかりやすく説明しますね(笑)。
話を戻すと、どぶろくとは何なのかを改めて考えることは絶対に必要です。どぶろくは濾していないものとか、米でつくるもの、というのは違うと思いますし、私は答えを持っていませんが、どぶろくのあり方を皆で考えることで、楽しみながら深めていけばいい。
そしてこれは日本酒にとってもプラスです。外国人に説明していると、日本酒も酒税法の定義と文化的な定義にズレが出るところがあります。酒税法の定義が悪いということではなく、それだけで説明したのでは、なかなか人の心を掴めないと感じます。
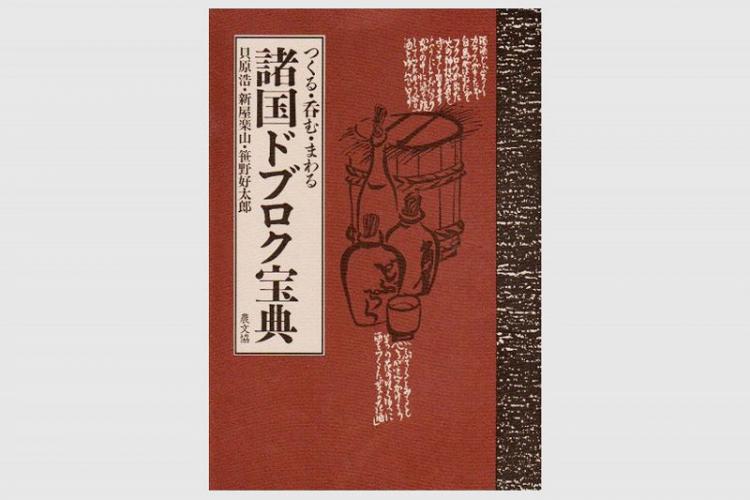
―酒税法は税を円滑に徴収するために酒類を分類したもので、歴史や文化的なバックボーンは考慮していません。文化としてはこのように定義づけられるけれど、税制ではこうなっていると言えばわかりやすいですね。
ジャスティン 日本酒の説明からどぶろくを排除しているから、日本の酒の歴史を捉えにくくなっていると思います。どぶろくを考えることでそのブランクが埋まるのではないでしょうか。日本酒の説明が難しくなるのは現在の酒から遡るからで、どぶろくから始めて、水酛(みずもと)が生まれて木桶が登場する。生酛の技術が開発されて、寒づくりになっていくと……という具合に酒造史に沿って説明していけば、日本酒は技術革新の連続だったんだ、なるほどそうやって発展してきたのかと腑に落ちます。
―たしかにその流れを抜きに生酛だけを取り出して説明するのは、どこがすごいのか、なぜ必要だったのかを言わずに、作業工程だけを話すことになり、聞く側も表面的なことを覚えるだけになりがちです。
ジャスティン それからどぶろくを伝えようとしてみて感じるのは、どぶろくをバックアップする体制がないということです。日本酒や本格焼酎は国税庁や酒造組合があり物心両面でサポートしています。どぶろくにはそうしたものがありません。文化をきちんとサポートする仕組みがないから、規格の議論はなく教育の場もできず、整理されないまま、どうしよう、どうしようと言っているだけになってしまっていると感じます
―どぶろくは生産者も零細なので、何をやるにも資金面は容易ではありません。2010年にどぶろくのコンテストをやりましたが、採算は厳しく続けられませんでした。今後はクラウドファンディングを活用するなどして広く支援を募りつつ、自治体や農業サイドを巻き込んでいくのではないかと思います。
ジャスティン ええ、「どぶらぶ」はそうした基盤づくりを進めることも狙っています。
―今日お聞きしたお話は日本の酒を考えるうえで示唆に富んだものと思います。ご協力ありがとうございました。
(聞き手:山田聡昭)

記事の情報は2024年6月20日時点のものです。
『さけ通信』は「元気に飲む! 愉快に遊ぶ酒マガジン」です。お酒が大好きなあなたに、酒のレパートリーを広げる遊び方、ホームパーティを盛りあげるひと工夫、出かけたくなる酒スポット、体にやさしいお酒との付き合い方などをお伝えしていきます。発行するのは酒文化研究所(1991年創業)。ハッピーなお酒のあり方を発信し続ける、独立の民間の酒専門の研究所です。
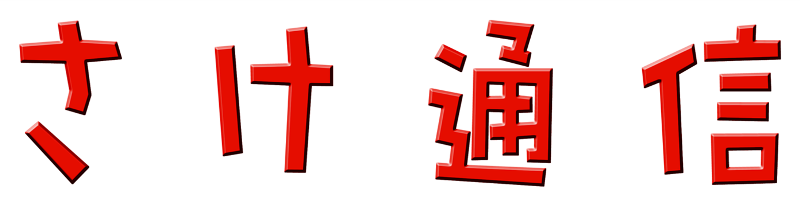
- 1現在のページ
 山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)
山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)